
「日産 クリッパー 運転しにくい」と検索している方の中には、「どんな車なのか詳しく知りたい」と感じている方も多いのではないでしょうか。
日産クリッパーは軽商用バンとして長く支持されてきたモデルで、現在の新型モデル「クリッパーバン」は、スズキのエブリイをベースにしたOEM車として製造工場で生産されています。
この記事では、クリッパーの評判や実際に運転しにくいとされる理由、そしてそれを改善するための具体的な対策まで、わかりやすく解説していきます。DXやGXといった各グレードの違いや、NV100時代との比較、さらには5AGSやCVTなどのオートマの特徴にも触れていきます。
また、ターボモデルの走行性能や燃費が悪いと感じる場面の背景、価格帯ごとの装備差、さらにはカスタムや中古購入時の注意点まで、幅広い視点から情報を整理しました。
クリッパーに興味はあるけれど運転のしやすさが気になる方や、新型と旧型の違いを知って納得して購入したいという方にとって、役立つ情報が詰まった内容となっています。
- 日産クリッパーが運転しにくいと感じる具体的な理由
- 各グレードやトランスミッションの違いと特徴
- 運転しやすくするためのカスタムや工夫
- 中古車選びや購入時に確認すべきポイント
日産クリッパーが運転しにくいと感じる理由

- OEMや製造工場の背景とは
- 価格帯とグレードごとの違い
- 燃費が悪い?
- オートマの性能と快適性を比較
- カスタムで運転しやすくできる?
- ターボモデルの走行性能について
- 中古購入時の注意点と選び方
どんな車か?基本情報と評判まとめ

日産クリッパーは、軽商用バンとして設計された車であり、主に仕事で荷物を運ぶシーンで活躍する一台です。初代モデルは2003年に登場し、現在はスズキ「エブリイ」のOEM車として製造されています。現行モデルの車名は「クリッパーバン」となっており、名称や仕様も時代と共に進化してきました。
主な特徴としては、全長3.4m以下・全幅1.5m以下というコンパクトサイズながらも、最大積載量350kgという高い積載性能を持つ点が挙げられます。また、全車寒冷地仕様となっており、過酷な環境でも安心して使用できる設計になっています。
評判については、「取り回しがしやすい」「荷物がたくさん積める」といった声が多く聞かれます。一方で、加速力や乗り心地については軽バン特有の課題もあり、「高速道路では非力に感じる」といった意見もあります。
このように、日産クリッパーは多機能で実用性の高い軽バンとして、業務用だけでなくアウトドアやレジャー目的で利用する人にも一定の人気があります。
運転しにくさの原因と対策を解説

日産クリッパーが「運転しにくい」と言われる理由には、いくつかの要因が関係しています。特に目立つのは車高の高さ、エンジンの非力さ、視界の制限といった軽バン特有の構造的な特徴です。
まず、車高が高いことは荷室スペースを確保するために必要な設計ですが、横風の影響を受けやすく、カーブ時に車体が揺れることがあります。また、660ccのエンジンではパワーが限られており、特に登坂や高速走行時にはもたつきを感じやすいという欠点があります。
視界に関しても、コンパクトなキャビンに機能を詰め込んでいるため、運転席からの見通しがやや狭く感じることがあるでしょう。特に初心者や背の高いドライバーは、慣れるまでに時間がかかる可能性があります。
これらに対処するためには、まずシートとミラーの位置をしっかり調整して死角を減らすことが基本です。また、カーブや車線変更時には速度を落として慎重に運転することが求められます。穏やかなアクセル操作や、こまめな休憩を取ることも、運転の疲労を軽減し、快適さにつながります。
つまり、運転しにくさは車の性質上ある程度仕方ない部分もありますが、適切な運転方法やメンテナンスによって、十分に対処できる要素でもあるのです。
新型モデルと従来型の違いとは

新型クリッパーバンと旧型NV100クリッパーには、複数の違いがあります。特に大きな変更点は、トランスミッションとエンジン性能です。
旧型では4速ATや5AGS(自動MT)が搭載されていましたが、新型ではCVT(無段変速機)に置き換えられています。CVTは、より滑らかな加速と燃費性能を実現できるため、ストップ&ゴーが多い市街地走行には特に適しています。対して、5AGSは価格の安さや燃費の良さが魅力でしたが、シフトチェンジ時のクセや乗り味に慣れが必要でした。
エンジンについても、旧型はSOHC(シングルオーバーヘッドカム)を採用していましたが、新型ではDOHC+VVT(可変バルブタイミング)に変更され、低回転域でもトルクが出やすく、加速性能が向上しています。
また、最小回転半径も4.3mから4.1mへと縮小されており、小回り性能がさらにアップしています。狭い道路での取り回しや車庫入れがよりスムーズになった点は、日常使いの上で大きな利点といえるでしょう。
これらの違いから、新型は運転のしやすさや燃費性能、安全装備の充実度において、明らかにアップグレードされたモデルと言えます。特にこれから購入を検討している方にとっては、より安心で快適な選択肢になるでしょう。
DX・GX・NV100の違いをチェック

日産クリッパー(現・クリッパーバン)には複数のグレードがあり、主に「DX」「GX」「NV100クリッパー(旧モデル)」に分類されます。それぞれ装備や快適性、価格に違いがあるため、用途に合わせた選び方が重要です。
まず「DX」はエントリーモデルにあたるグレードで、価格が最も抑えられています。シンプルな装備が特徴で、主に業務用途を想定して作られています。ただし、電動格納ミラーが非搭載であったり、ボディカラーが限定的だったりと、利便性よりも実用性を重視した仕様となっています。
次に「GX」は上位グレードで、利便性や安全装備が大きく向上しています。例えば、リヤパワーウィンドウやリヤヒーター、インテリジェントエマージェンシーブレーキなどが標準装備となっており、快適性と安全性を求めるユーザーに適しています。荷室の広さや積載能力はDXと大きく変わりませんが、シートの質感や収納スペースなど細部の仕上がりが異なります。
「NV100クリッパー」は、旧型モデルとして販売されていた車種です。グレード構成や装備内容は現在のクリッパーバンに似ていますが、トランスミッションは4ATや5AGSが中心で、現行のCVT搭載モデルに比べて燃費やスムーズさでは一歩劣ります。また、エンジンも旧式のSOHCタイプで、最新のDOHC+VVTエンジンほどのトルクや効率性は期待できません。
このように、グレードによって装備や性能に差があるため、「価格重視」なのか「快適性重視」なのかで選択肢は大きく変わってきます。
5AGSの評判はどう?特徴と注意点

5AGSは、マニュアルトランスミッションをベースに、クラッチ操作と変速操作を自動化したトランスミッションです。オートマのように運転できるものの、構造的にはMTに近く、他のATやCVTとは挙動が異なります。
主な特徴は、変速段数が5速と多く、燃費性能に優れている点です。さらに、マニュアルモードが使えるため、ギア操作を自分でコントロールしたいという人にも向いています。また、クラッチ交換が可能であるため、消耗した際の修理費を抑えやすいという利点もあります。
ただし、慣れないと運転時に違和感を覚える人も少なくありません。例えば、シフトアップ時に一瞬駆動力が抜ける感覚があり、スムーズな加速とは言いにくい場面があります。加えて、駐車場などでの微妙な操作時には、クリープが弱かったり、半クラッチの動作が不安定に感じるケースもあります。
さらに、構造的にMTに近いため、クラッチ盤は消耗品とされており、故障の際は保証対象外になることもあります。実際に20万km前後で不具合が出るケースもあり、走行環境によっては長期使用に向かない可能性も考慮しておくべきです。
このような特性を理解せずに購入すると「乗りにくい」と感じやすくなるため、購入前には試乗し、変速の感覚やクセに慣れるかどうかを確認するのがおすすめです。価格や燃費を重視するなら魅力的な選択肢ですが、快適性を求めるならCVTや4ATの方が合っているかもしれません。
日産クリッパーが運転しにくい時の選び方

- OEMや製造工場の背景とは
- 価格帯とグレードごとの違い
- 燃費が悪い?
- オートマの性能と快適性を比較
- カスタムで運転しやすくできる?
- ターボモデルの走行性能について
- 中古購入時の注意点と選び方
OEMや製造工場の背景とは
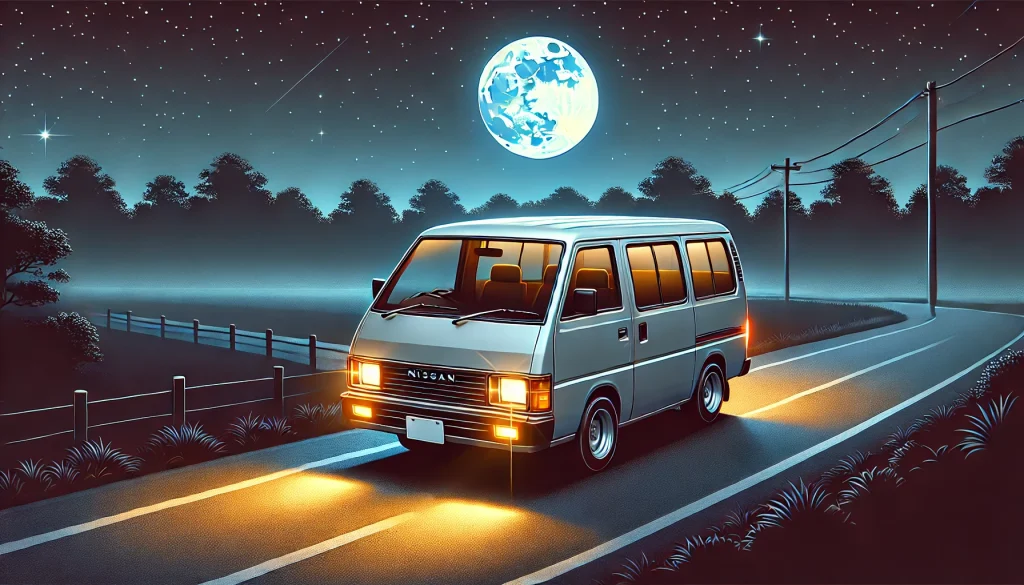
日産クリッパー(現・クリッパーバン)は、実は自社開発ではなく、他社からのOEM供給を受けて販売されている軽バンです。OEMとは「Original Equipment Manufacturer(相手先ブランド製造)」の略で、他メーカーが設計・製造した車両に、別メーカーのブランドやロゴを付けて販売する方式を指します。
クリッパーはもともと三菱「ミニキャブ」のOEM車として2003年に登場しました。その後、三菱が軽商用車の生産から撤退したことに伴い、2013年からはスズキの「エブリイ」をベースにしたOEM供給に変更され、現在もこの体制が続いています。
製造はスズキの工場で行われており、エブリイと同じ生産ラインで組み立てられています。つまり、クリッパーとエブリイは中身がほぼ同じ車といえますが、細部のデザインや装備、販売体制が日産仕様にアレンジされている点が異なります。
OEMを利用するメリットは、コストを抑えつつ幅広い車種を揃えられることです。日産にとっても、軽自動車市場に参入し続ける上で合理的な手段となっています。ユーザーにとっては、信頼性の高いスズキ製の車を日産ブランドで購入できるという点も安心材料のひとつになるでしょう。
価格帯とグレードごとの違い

日産クリッパーバンの価格帯は、おおよそ130万円台から200万円前後まで幅があります。これは、グレードや駆動方式、トランスミッションの種類によって価格が変動するためです。
エントリーグレードの「DX」は最も安価で、2WDの5MT仕様であれば約133万円からスタートします。装備は必要最低限に抑えられているものの、業務用途には十分な実用性を備えています。一方で、4WDやCVTを選ぶと価格は140万円台後半〜150万円程度に上昇します。
「DX GLパッケージ」は装備を少し充実させたグレードで、電動格納ドアミラーや集中ドアロックが追加されます。このグレードでは4ATのみの設定となっており、価格はおよそ158万円〜174万円となっています。
中間グレードの「GX」は、内外装の質感や安全装備が大きく強化されており、パワーウィンドウやリアヒーター、分割可倒式のリアシートなどが搭載されます。価格は160万円台から180万円前後に設定されています。
最上位グレードである「GXターボ」は唯一のターボエンジン搭載車で、高速走行や長距離移動に向いています。装備面も充実しており、価格は2WDで約185万円、4WDでは200万円を超える設定です。
このように、用途や求める装備レベルによって適したグレードが異なります。コストを重視するなら「DX」、快適性や走行性能を重視するなら「GX」や「GXターボ」が選択肢となるでしょう。
燃費が悪い?

クリッパーバンは軽自動車でありながら積載性を重視した設計になっているため、一般的な軽乗用車と比べると燃費が劣ると感じる場面があります。しかし、これは必ずしも「燃費が悪い」と断言できるものではなく、使用環境や車種特性を理解することが重要です。
現行モデルのWLTCモード燃費は、5MT車で16.9~17.2km/L、CVT車で16.4km/Lとなっています。一方、ターボモデルの「GXターボ」は13.1km/Lとやや低めです。これは、荷物を多く積む用途や走行性能を重視したターボ仕様ならではの数値であり、性能とのバランスを考えれば納得の範囲内です。
また、旧型の4ATや5AGS搭載モデルは走行環境によって燃費がばらつきやすく、渋滞や頻繁なストップ&ゴーが多い都市部では実燃費が悪化する傾向があります。5AGSは燃費に優れる一方、乗り方によっては逆に伸びないこともあるため、クセを理解した運転が求められます。
燃費が気になる方には、以下のような工夫が効果的です。例えば、エアコンの使用を最小限にする、不要な荷物を積みっぱなしにしない、急発進や急ブレーキを避けるなど、日常的な運転の見直しだけでも燃費は改善されることがあります。
つまり、クリッパーバンの燃費は「悪い」のではなく、車の性格を理解して上手に使えば、十分実用的な燃費性能を発揮してくれるというわけです。
オートマの性能と快適性を比較

日産クリッパーに採用されているオートマには複数の種類が存在し、それぞれ性能や乗り心地に違いがあります。主に使われてきたのは「4AT」「5AGS」、そして現行モデルに搭載されている「CVT(無段変速機)」の3タイプです。
まず、4ATは昔ながらのトルクコンバーター式で、スムーズな加速と信頼性が特徴です。ただし変速段数が少ないため、加速性能や燃費性能は限定的で、高速走行では回転数が上がりやすくなります。
5AGSは、MTをベースに自動変速機能を加えた変わり種です。理論上は5速あることで理想的な変速が可能ですが、変速時に一瞬パワーが抜けるような感覚があり、慣れるまでは運転に違和感を覚えることがあります。価格が安く、燃費にも優れますが、滑らかさや快適性の面では賛否があります。
一方、現行型に採用されたCVTは、加速時のギクシャク感がなく、エンジンの回転数を効率的に調整してくれるため、市街地や坂道での走行もスムーズです。ストレスのない走りを求めるならCVT搭載モデルの方が快適性は高く、初心者ドライバーにも扱いやすいと言えるでしょう。
このように、それぞれのオートマにはメリットとデメリットがあるため、使用環境や重視するポイントに応じて選ぶことが大切です。
カスタムで運転しやすくできる?

日産クリッパーは商用車として設計されているため、必要最低限の装備で構成されています。とはいえ、後付けのカスタムを施すことで、運転のしやすさを大きく向上させることができます。
例えば、運転中の視界をサポートするアイテムとして「補助ミラー」や「バックカメラ」を装着することで、死角が減り駐車時の不安も軽減されます。とくにバックモニターは、慣れていない方にとっては大きな安心材料になるでしょう。
また、シートクッションの追加やハンドルカバーの装着といった小さな工夫でも、長時間運転時の疲労軽減につながります。さらに、ドライブレコーダーを装着することで、万一の事故にも備えることができ、安全面でもプラスに働きます。
ただし、商用バンは装備のカスタムに制限がある場合もあるため、選ぶパーツは車両のサイズや構造に適したものを選ぶことが重要です。純正品だけでなく、社外品でもクリッパーに対応しているパーツは多く出回っているので、選択肢も豊富です。
このように、カスタムをうまく活用すれば、商用車ベースのクリッパーでも、より快適で運転しやすい1台に仕上げることが可能です。
ターボモデルの走行性能について

クリッパーのターボモデルは「GXターボ」としてラインナップされており、シリーズ唯一のターボエンジンを搭載した仕様となっています。走行性能においては、他のグレードよりも一歩リードしているといえるでしょう。
軽バンにありがちな「パワー不足」を感じさせない点がターボの最大の魅力です。特に登坂や合流、荷物を多く積載した状態でも、ターボの加速力によりスムーズな走行が可能となります。また、高速道路でのクルージングも安定しており、長距離移動が多い方には適した選択肢です。
一方で、燃費については自然吸気エンジンに比べてやや劣る傾向があります。GXターボのWLTCモード燃費は13.1km/Lと、他グレードの16km/L前後と比べて数字に差が出ています。また、車両価格も最上位となっており、2WDで約185万円、4WDでは200万円超となります。
とはいえ、パワーと安定性を重視する方にとって、ターボモデルは快適なドライブを支えてくれる心強い存在です。特に荷物を多く積む機会が多い方や、坂の多い地域での使用を想定している方にはおすすめです。
中古購入時の注意点と選び方
日産クリッパーを中古で購入する際には、いくつかのポイントを押さえておくと安心です。特に商用車という特性上、過去の使われ方や走行距離、メンテナンス履歴が車の状態に大きく影響します。
まず確認したいのは、走行距離と整備記録簿の有無です。軽商用車は仕事で酷使されることが多く、過走行の車両も多く見受けられます。10万kmを超えていても整備が行き届いていれば問題ないケースもありますが、エンジンやミッションの状態は念入りにチェックしたいところです。
また、旧型モデルでは「5AGS」「4AT」といった特有のトランスミッションが採用されており、動作にクセがあることもあります。これらは好みが分かれるため、できれば購入前に試乗して感触を確かめておくと良いでしょう。
さらに、外装や内装の劣化状況も確認ポイントです。商用車は内装にキズや汚れが付きやすく、荷物の積み降ろしでリアゲート周りが傷んでいることも少なくありません。
加えて、安全装備の有無もチェックしておきたい要素です。年式やグレードによっては自動ブレーキや車線逸脱警報が搭載されていないこともあるため、必要な機能が含まれているかを事前に把握しておきましょう。
こうした点を総合的に確認することで、後悔のない中古車選びができます。状態の良い個体を選べば、中古のクリッパーでも十分に活躍してくれるはずです。
日産クリッパーが運転しにくいと感じる理由と対策の総まとめ
- 日産クリッパーは軽商用バンとして高い積載力と小回り性能を持つ
- 現行モデルはスズキ・エブリイのOEMで、信頼性のある設計
- 高さのある車体は横風に弱く、安定性に影響を与えることがある
- 視界がやや狭く、初心者や高身長ドライバーには慣れが必要
- 660ccエンジンは市街地向けで、高速では非力に感じやすい
- CVTは滑らかな走りが可能で、従来の4ATや5AGSより快適
- DXは価格重視で装備がシンプル、業務用途に適している
- GXは快適性と安全性を重視したバランスの良いグレード
- GXターボは登坂や荷物の多い運転時に力強さを発揮する
- 5AGSは燃費に優れるが運転には慣れが必要でクセがある
- OEM供給によりコストを抑えつつラインナップを維持している
- 実燃費は走行環境によりばらつきがあり、使い方に左右される
- 視界補助パーツやシート改善などカスタムで運転性を高められる
- 中古購入時は走行距離・整備履歴・安全装備の有無を要確認
- 小回りの良さと荷室の広さは都市部での使用に向いている








